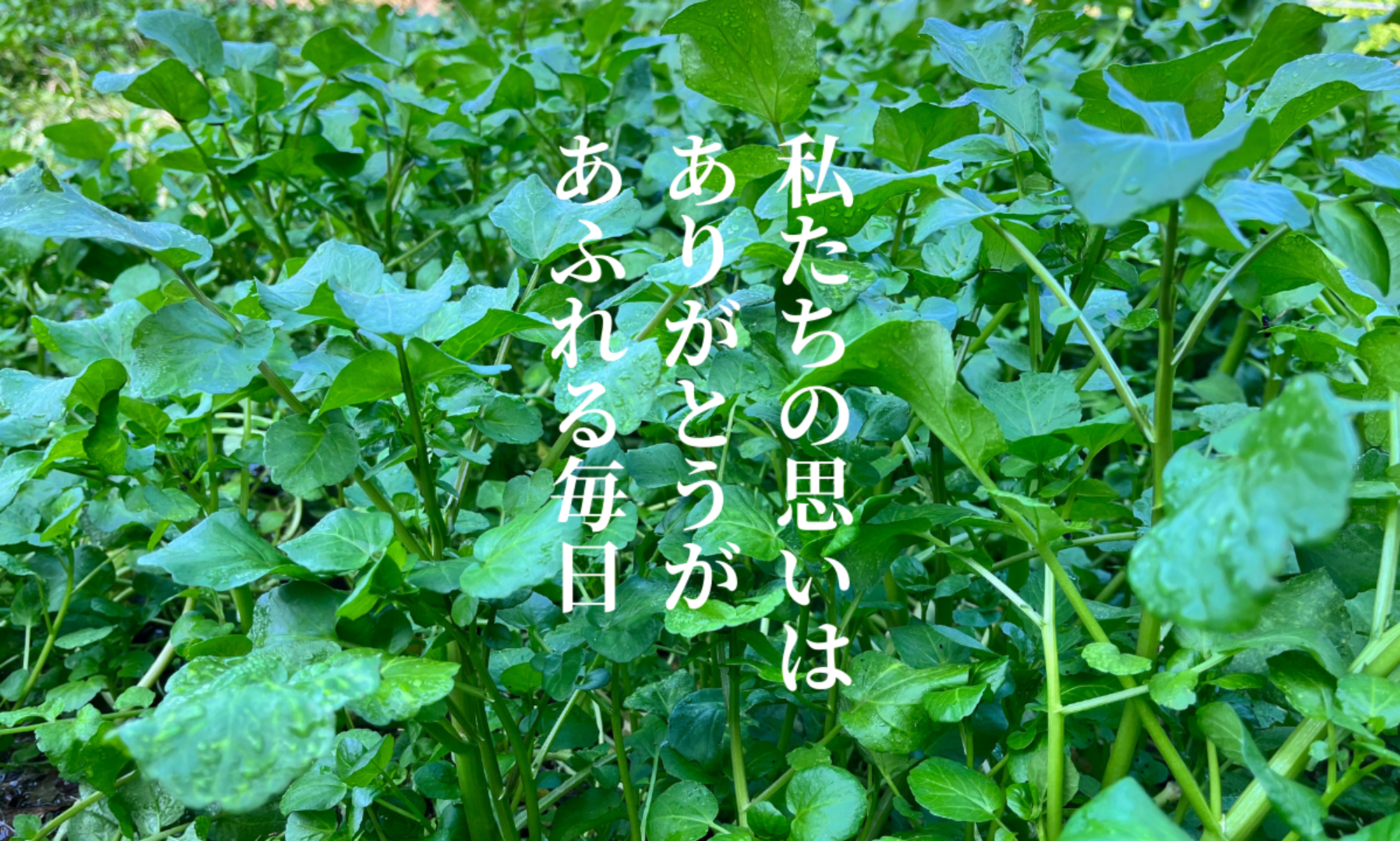CBDは植物の大麻草に含まれれる栄養素「カンナビノイド」のひとつです。
大麻草にはビタミンなど500種類以上の成分が含まれており、その中でも大麻草のみに含まれている栄養素を「カンナビノイド」と言います。カンナビノイドにはCBD(カンナビジオール)のほかに、THC(テトラヒドロカンナビノール)・CBG(カンナビゲノール)・CBN(カンナビノール)など140種類ほど見つかっています。

ヘンプとカンナビノイド(CBD)
ヘンプとは産業用に使用する麻の総称で、種子と茎※1でCBD成分が20%以上、THC含有量が0.3%未満の品種が産業用の利用として栽培が認められています(マリファナとは別物)昨今ではプラスチックや樹脂製品など、某自動車メーカーの内装などの工業製品にヘンプが使用されています。

※1 日本では大麻取締役法により、THC(マリファナ成分)を多く含む穂・葉・根・枝の利用は禁止されています(2021年より、部位別規制から成分規制に変更)
一方でCBDは、THC成分を一切含まない栄養素で、抗炎症作用や自律神経調節、免疫調節、抗てんかんなど、多くの効用が認められており今後様々な疾患への応用が期待されます。
CBDの安全性
日本では大麻草に対する誤解からカンナビノイド(大麻草の栄養素)のCBDに疑問を感じている人も多いのが実情です。
古来より我々日本人は麻を大事にしてきました。麻は精神性向上はもとより、神事に使用される程身近でかつ貴重なものでした。麻は土壌を浄化し、浄化した土壌から大地の恵みを体内に取り込む。古来より大事にしてきた歴史があります。その名残として、全国各地に「麻」のつく地名が今も多く存在しています。
一方で大麻は悪とする教育の徹底で、今でも覚せい剤や麻薬と同列に扱われイメージは損なわれるばかりです。でも実際に問題となるのは大麻草に含まれるマリファナ成分の「THC」だけなのです。
そのマリファナについても、薬理学で示す中毒性の強さと法律の規制に大きな不一致があります。つまり、薬理学での中毒性の評価と法律の規制の違いが現状の混乱を招いているのです。

CBDの効果
CBDには身体が健康に生きるための神経系の働きや免疫系の働きに深く関わっています。
不思議なことに私たちの身体にはカンナビノイドに反応する身体調節機能が存在します。それがエンド・カンナビノイド・システム(ECS)です。これは私たちが健康に生きるために欠かせない免疫活性や脳神経伝達システムなど、重要な働きです。
このECSは1988年に発見されました。さらに1990年代、ECSで機能する体内物質が発見されます。それが「アナンダ二ミド」と「2-AG(2-アラキドノイルグリセロール)」です。これらは体内で生成される物質で内因性カンナビノイドと呼ばれ、対してCBDは外因性カンナビノイドと呼ばれています。その内因性カンナビノイドに反応する受容体(鍵と鍵穴に例えるなら鍵穴に該当)が全身の細胞に存在します。その鍵穴は神経細胞(CB1)と免疫細胞(CB2)に多く含まれます。
全身の細胞の受容体に内因性カンナビノイドが鍵となり作用することで、細胞同士が活性化し、細胞や器官などの機能を調節しています。
つまり、細胞にある受容体(鍵穴)に、鍵に該当する内因性カンナビノイドや外因性カンナビノイドが結合することで作用を発揮しています。

アルツハイマーやかんてんの症状は、脳の神経伝達異常が原因とされています。CBDは神経伝達異常にも効果が期待でき、異常がある患部の受容体(鍵穴)に鍵として作用し、伝達異常を限りなく正常に戻すことで、炎症(疾患)が緩和されます。
現代社会の強いストレスや環境、加齢などの影響で内因性カンナビノイドは減少していきます。それが原因で体調不調や神経系、免疫系の炎症(疾患)が起きます。そこで、体内にもともとあるものが欠乏しているなら、外部から摂取し補う必要があります。そこに、外部からCBDを摂ることに意味と価値があると期待されています。
現在、CBDの効果が期待される27の疾患は以下になります。
・依存症 ・筋委縮性側索硬化症(ALS) ・ぜんそく ・自閉症 ・アルツハイマー病 ・注意欠陥多動症(ADHD) ・不安神経症 ・関節炎 ・自己免疫疾患 ・うつ病 ・ガン ・糖尿病(Ⅰ型Ⅱ型) ・脳しんとう ・線維筋痛症 ・片頭痛 ・炎症性腸疾患 ・多発性硬化症 ・悪心/嘔吐 ・ニューロパチー ・肥満 ・疼痛 ・パーキンソン病 ・総合失調症 ・心的外傷ストレス症候群(PTSD) ・皮膚病 ・発作性疾患(かんてん症候群) ・睡眠障害
CBDは大麻草から抽出された天然の成分です。毒性はなく安全です。
thankfuldays